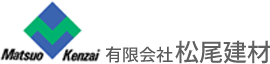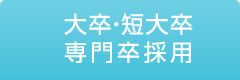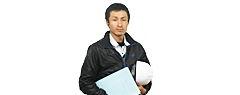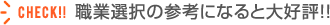2022年07月13日暑中コンクリート|建築工事③
【品質】
a.コンクリートの品質は、3節によるほか、
スランプ、空気量、圧縮強度などは、高温環境下での変動要因を考慮して定める。
コンクリート温度が高いほど、
スランプ・空気量は所要の値が得られにくく、
時間経過にともなうそれらの低下も大きくなります。
また、ブリーディング量はコンクリート温度が
高くなるほど減少し、凝結・硬化は早められます。
硬化コンクリートについては、
高温になるほど初期材齢の強度発現は促進されるが、
反面、長期強度での強度増進は小さくなります。
フレッシュコンクリートも硬化コンクリートも
高温による影響を受けやすいので、事前に十分な検討を行って
所要の品質を定めるとともに、コンクリート生産者(生コン工場)と
協議して、品質の確保に務めなければならないと規定されています。
b.荷卸し時のコンクリート温度は、原則として35℃以下とする。
この規定は、建築・土木ともに共通しています。
高温の影響は上記で挙げたものだけでなく、
こわばりが生じて均しが困難になる、
コールドジョイントが発生しやすくなる、
打ち込んだコンクリートが冷めるときの容積変化が大きくなり
ひび割れが発生しやすくなるなどの問題があるため、
荷卸し時のコンクリート温度はできるだけ低くすることが
望ましいとされています。
コンクリートの練上がり温度は、
地域や使用材料の温度により若干の相違はあれど、
一般に平均気温より5℃高くなると言われています。
また、練上がりから荷卸しまでのコンクリートの
温度上昇は2~4℃程度とされていて、
暑中コンクリート工事の適用を開始する平均気温25℃に対応する
荷卸し時のコンクリート温度は、現場での対応を考慮して、
35℃以下を原則することと示されています。
c.荷卸し時のコンクリート温度が35℃を超えないように材料・調合を変更したり、
材料やコンクリートを冷却したりする場合、それらの方法については、工事監理者の承認を受ける。
暑中コンクリートの適用期間中に、平均気温が26~28℃を超える場合には、
荷卸し時のコンクリートの温度が35℃を超える可能性が高くなります。
荷卸し時のコンクリート温度が35℃を超えないように、
材料・調合の変更、使用材料の温度制御、
コンクリートの冷却などの対策を講じる場合には、
その方法について工事監理者の承認を受けなければいけません。
具体的には、
・水温の低い地下水などの使用
・低発熱型セメント、フライアッシュなどの混和剤の使用
・冷却設備を有するレディーミクストコンクリート工場の選定
・現場までの運搬時間の短いレディーミクストコンクリート工場の選定
・液体窒素などを用いたコンクリートの冷却
といった対策が考えられます。
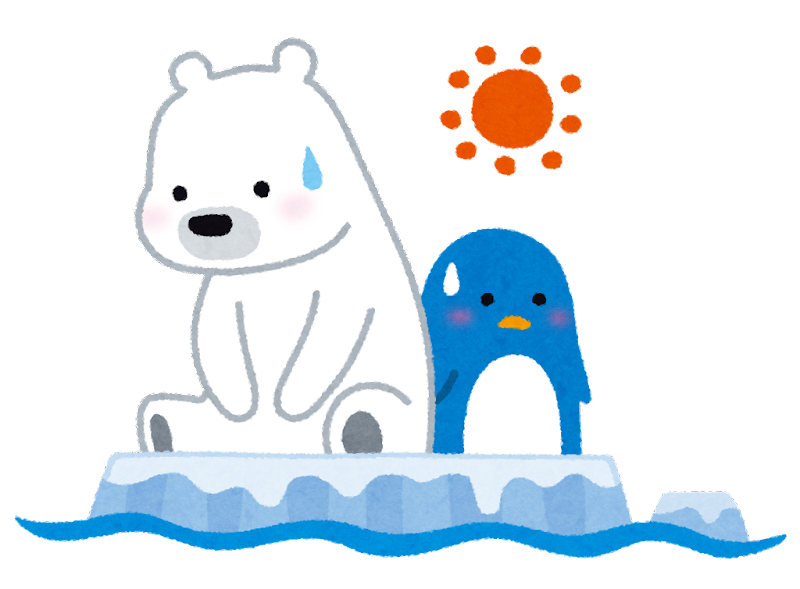
d.荷卸し時のコンクリート温度が35℃を超える場合において、
工事監理者とコンクリートの品質変化に対する対策を講じておく。
近年、各地の気温は高くなる傾向にあり、
c.による対策を講じても荷卸し時のコンクリートの温度が
35℃を超えることが避けられない事態も予想されます。
これに備えて、材料・調合の見直し、施工時間の短縮、養生期間の延長などにより、
コンクリートの施工性の確保、構造体コンクリートの品質確保に対する方策を
工事監理者と講じておく必要があります。
具体的には、
1.コンクリートの施工性の確保
・従来よりも高い機能を有するAE減水剤、高性能AE減水剤標準形または遅延形の使用
・練混ぜから打込み終了までの時間の短縮、打重ね時間間隔の短縮
2.構造体コンクリートの品質確保
・低発熱型セメント、フライアッシュなどの混和剤の使用(温度上昇の抑制および長期強度の増進)
・散水・噴霧養生の採用や養生期間の延長
といった対策が考えられます。
また、土木工事と同じように、建築工事でも38℃上限説が言及されており、
「適切な対策を講じることにより、荷卸し時のコンクリートの温度が38℃程度までであれば、
35℃の場合と比べて極端な性能低下が生じないことが示されてきている。」と明示されています。
2022年07月12日暑中コンクリート|建築工事②
【施工計画】
施工者は、暑中環境における以下の事項に配慮して
品質管理計画および施工計画を立案し、工事監理者の承認を受ける。
(1)コンクリートの品質の悪化
(2)作業員の体力の消耗と作業能率の低下
暑中コンクリートの打設には、
常に上記の2つの問題点がつきまといます😕
コンクリートの品質悪化を防ぐ対策としては
工事監理者の承認の下、コンクリートの全段階において、
高温の影響が最小となるように十分な検討を行って
施工計画書を作成することが挙げられます。
そして、適切な計画の下、施工が行われた場合には
構造体コンクリートの品質は、作業者の能力と
連携によって大きく左右されます👬🏻
日本の夏のような、高温多湿の環境下では、
体力を消耗して疲労しやすく、
品質低下を招くおそれがあるだけでなく、
熱中症による死亡災害につながる危険性もあります🤒

そのため、品質を追求するばかりでなく、
作業環境、作業員の健康管理および安全を考慮した
打込み体制を定めることが重要です!
この対策として、適切な休息を各人が
交代で取れるような休息方法を設定するほか、
気温が高くなる時間帯を避けて、早朝または夕方以降への
打込み時期の変更などの対策も有効だと示されています。
弊社でも、打設予定日より前に余裕をもって
ご相談いただければ、早朝からの出荷のご要望にも
誠意対応させていただいております🌅🐓
ぜひ、お役立ていただければ幸いです!
2022年07月11日暑中コンクリート|建築工事①
前回、土木工事における
暑中コンクリートの規定・注意点・対策を、
土木学会 2017年版 コンクリート標準示方書【施工編】に
沿ってご紹介いたしましたが、
今回からは、建築工事における
暑中コンクリートの規定・注意点・対策を、
日本建築学会 2018年版 建築工事標準仕様書・同解説
JASS5 鉄筋コンクリート工事 に沿ってご紹介いたします😄
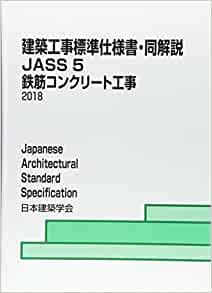
【総則】
a.本節は、暑中コンクリート工事に適用する。
暑中コンクリート工事の適用期間は、特記による。
特記のない場合は、下記b.により定め、工事監理者の承認を受ける。
土木工事と同じく、建築工事においても
夏期に施工されるコンクリート工事は、気温が高いことや日射の影響で
コンクリート温度が高くなり、ワーカビリティーや耐久性の低下など
種々の問題が発生しやすい状況にあります。
その対策を行うためのコストが必要となることが考慮された結果、
暑中コンクリート工事として施工を行う期間は、特記によって
指定することとなっています。また、特記のない場合には、下記の
b.により適用期間を定め、工事監理者の承認を得ることが
必要と規定されています。
b.暑中コンクリートの適用期間は、
日平均気温の平年値が25℃を超える期間を基準とする。
暑中コンクリート工事を適用する期間は、
特記のない場合、「日平均気温の平年値が25℃を超える期間」を
基準として定めると規定されています。
土木工事では、「日平均気温が25℃を超える期間」とされていました。
「平年値」とは、西暦年の一の位が1の年から30年後の一の位が0で終わる年まで、
30年間分の気象データについて算出した平均値のことをいうそうです。
現在、「平年値」として使われているデータは、1991年~2020年の間の平均値になります。
気象庁|報道発表資料 平年値の更新について ~平年値(統計期間1991〜2020年)を作成しました~
なお、近年の気候変動の影響で、平年値から得られた適用期間の日数の差が
この10年間で大きくなる傾向にあり、より正確な設定を行うためには、
直近の測定データから25℃を超える期間を予測する方法が考えられます。
全国的に見れば、新しい気温の平年値はこれまでの平年値と比較して、0.1℃から0.5℃高くなっており、
直近10年で見ると、地域によっては、これまで暑中としてきた期間よりも前後10日間程度長くなる場合もあるそうです。
したがって、暑中期間の設定は、気候変動も考慮して安全側の設定とすることが望ましいとされています。
2022年07月08日看板がつきました!
骨材置場に、
骨材の名前と数量あたりの単価を
表示する看板を作っていただきました!

とっても見やすくて、わかりやすくなりました😄
2022年07月07日七夕🎋
今日は、七夕ですね!
社員のお子さんがぬりえをされていたので、
撮らせてもらいました😄📸

明日からは雨が続くみたいですが、
今晩はお天気がよさそうです!
天の川見られるといいですね🌌🧡
2022年07月07日暑中コンクリート|土木工事編⑤
暑中コンクリート|土木工事編 ラストです!
★コンクリートの打込みを終了したときには、
速やかに養生を開始し、コンクリートの表面を乾燥から
保護しなければならない。また、特に気温が高く湿度が
低い場合には、打込み直後の急激な乾燥によってひび割れが
生じることがあるので、直射日光、風等を防ぐために
必要な処置を施さなければならない
暑中コンクリートでは、打ち込まれたコンクリートの表面は、
直射日光や風にさらされると急激に乾燥し、仕上げが困難になる
ばかりではなく、ひび割れを生じる可能性が高くなります。
このため打込みを終了したコンクリートは、
露出面が乾燥しないように速やかに養生することが大切です。
対策としては、
・打設後速やかにシートなどで養生し、水分逸散を防止する
・コンクリート打設後、散水もしくは噴水により水分を与えつつ冷却する
・コンクリート打設後、水を張る(湛水養生)
などの方法が有効とされています😃

大きな工場が多い首都圏には、こんな業者さんもおられるんですね!
また、乾燥が生じるおそれのある型枠を使用する場合には、
型枠も湿潤状態に保ち、さらに型枠を取り外した後も
養生期間中は露出面を湿潤状態に保つ必要があります。
なお、湿潤養生期間は、
日平均気温15℃以上として定められた日数を満足することを
標準とし、施工条件等を加味して適切に定めることが重要です。
特に気温が高く、また、湿度が低い場合には、表面が急激に乾燥し
ひび割れが生じやすいので、散水または覆い等による適切な処置を行い、
表面の乾燥を抑えることが大切です!
次回からは、日本建築学会 JASS5に沿って
建築・鉄筋コンクリート工事における
暑中コンクリートの標準について解説します!
2022年07月06日暑中コンクリート|土木工事編④
今回も、暑中コンクリートについて
土木学会 2017年版 コンクリート標準示方書【施工編】に沿って
解説していきます!
暑中コンクリートとしての打設になるかどうかは、
「日平均気温」によって規定されていますが、
コンクリート温度の範囲はどうなっているのでしょう?
★打込み時のコンクリート温度の上限は、35℃以下を標準とする。
コンクリート温度がこの上限値を超える場合には、
コンクリートが所要の品質を確保できることを確かめなければならない
コンクリートの打込み温度が高いと、
運搬中のスランプの低下、連行空気量の減少、
コールドジョイントの発生、表面の水分の急激な蒸発による
ひび割れの発生、温度ひび割れの発生等の危険性が増します。
このため、コンクリートの打込み温度はできるだけ低いほうが
望ましいとされます。
しかし、コンクリートの品質に及ぼす高温の影響は、
コンクリートの打込み温度のみで一義的に決まるものではなく、
環境条件(外気温、湿度、風速、日射等)
構造物条件(打込み箇所の面積、厚さ、拘束の度合い等)
コンクリートの条件(セメントや混和剤の種類等の材料、水セメント比、スランプ等)
施工条件(打込み前の状態、打込み速度、打込み時の日よけ、養生方法等)
が複雑に関係し合っています😖
したがって、それらを考慮した施工計画を立てることが重要であり、
計画で設定した打込み温度を超えることが予想される場合には、
計画を見直し、適切な対策を講じることが必要となります。

しかし、工期面、レディ―ミクストコンクリート工場の設備面、
周辺住民への騒音・安全面等の制約もあって、実際には対策を
必ずしも十分に実施できないことも多いため、
これまでの実績から、一般的な条件下では打込み温度が
35℃以下であればコンクリートの品質への影響は少ないと判断できるため、
打込み時のコンクリート温度の上限が35℃以下であることを
土木学会では、標準として定めています。
ただ、昨今では夏期の外気温は全国的に高くなりつつあり、
コンクリート温度は、荷卸しから打込み終了までには2℃程度
上昇するため、打込み終了時に35℃以下であることを満足するのが
難しい工事もあります。
このような場合には、以下のような事項を事前に検討し、
コンクリートが所要の品質を確保できることを確認する
必要があります。
1. フレッシュコンクリートの品質(スランプ、空気量および
それらの経時変化、ブリーディング、凝結時間等)に及ぼす
影響を確認する
高性能AE減水剤等の混和剤の技術資料では、試験室もしくは
コンクリートの温度が30℃の条件ではコンクリートの品質を確認していても
これを大きく上回る温度条件での品質に及ぼす影響は定かではない。
2.硬化コンクリートの強度に及ぼす影響を確認する
3.コンクリートの施工に及ぼす影響を確認する。
コンクリートの練混ぜ開始から打ち終わるまでの時間、
圧送によるスランプの低下、許容打重ね時間間隔、養生方法、
仕上げ時期等が定かでないため、試験等により確認して適切に定める。
4.コンクリートの打込み温度が高い場合には、想定した部材寸法より小さくても、マスコンクリートとしての取扱いが必要になる可能性があるため、温度ひび割れに対する照査を行う。
また、温度ひび割れに関する検討に基づくコンクリートの打込み温度の設定と管理を行う。
示方書では、セメントの種類ごとに終局断熱温度上昇量および
温度上昇速度の標準値を示しているが、打込み温度は30℃までを
想定しているため、断熱温度上昇特性を事前に試験により
確認しておく必要がある。
5.設計基準強度は50N/mm2未満であっても比較的富配合で、高強度コンクリートと同様に、初期の高温履歴によって構造物内のコンクリートの圧縮強度が標準養生した供試体の圧縮強度よりも小さくなる可能性がある場合には、高強度コンクリートの標準に従い、高温履歴が圧縮強度に及ぼす影響を試験により確認する
2022年07月05日暑中コンクリート|土木工事編③
今回も引き続き、
土木学会 2017年版 コンクリート標準示方書【施工編】に沿って
暑中コンクリートについて解説していきます。
※今回から打設等、お客様にご注意いただきたい内容になっております。
★コンクリートの打込みにあたっては、
コンクリートから吸水するおそれがある部分を
湿潤状態に保たなければならない。
また、直射日光を受けて高温になるおそれのある部分は、
散水、覆い等の適切な処置を施さなければならない
気温が高い場合や直射日光を受けて高温になる場合には、
地盤や木製型枠、既に打ち込まれたフレッシュコンクリート表面あるいは
硬化コンクリート表面(打継面)等は非常に乾燥しやすくなります。
乾燥は、打ち込んだコンクリートの流動性(充填性)や打重ね部における
一体性の低下(コールドジョイントの危険性)を招く可能性があるので、
散水を行うことや覆いをすること等により湿潤状態に保つ必要があります。

気温が高い時に表面を保護することなく1層目からの打ち重ね時間が空くと、
このように継ぎ目に豆板(ジャンカ)ができることが多くなります。
ただし、多量の残水はコンクリートの強度低下につながりますので、
型枠内に水がたまることがないように過度の散水は避け、打込み前に
型枠内の状態を確認して溜まった水を除去しなければなりません。
★コンクリートの打込みは、練混ぜ後
できるだけ早い時期に行わなくてはならない。
練混ぜ開始から打ち終わるまでの時間は、1.5時間以内を原則とする
暑中コンクリートでは、スランプは時間の経過に伴って
低下しやすいため、練り混ぜてから長時間経過したコンクリートは
打込みが困難になる場合があります。
一般に、練混ぜから1.5時間以内であれば、スランプの低下量も小さく、
問題なく打ち込むことができるとされています。
しかし、このような品質の変化は、気温の上昇とともに
増大する傾向にあるため、コールドジョイント等が生じないよう、
練り混ぜてからできるだけ早く連続的に打ち込むことが理想です。
標準示方書の中で、外気温が25℃を超える場合の
許容打重ね時間間隔は2.0時間以内と定められていますが、
日平均気温が25℃を超える暑中コンクリートの時期には、
この時間間隔よりも短く設定することが望ましいとされます。
2022年07月04日暑中コンクリート|土木工事編②
今回は、暑中コンクリートにおける「材料」について、
土木学会 2017年版 コンクリート標準示方書【施工編】に沿って
当社の取り組みをご紹介いたします!
★所定のコンクリート温度が得られない場合には、
事前に材料の温度を下げる方法を検討し、その効果を
確認しておかなければならない
骨材は、コンクリートの容積の内に占める割合が大きく
骨材温度がコンクリート温度に及ぼす影響も大きいとされます。
(通常、骨材温度±2℃につきコンクリート温度±1℃の変化)
長時間炎天下にさらされた骨材をそのまま用いると、
コンクリートの温度が40℃以上にもなり、所定のスランプを得るための
単位水量の増加や、運搬中におけるスランプの低下あるいは
打込み後における急激な凝結の進行等が生じることがあります。
そこで、骨材は、適当な施設により日光の直射を避ける必要があります。
松尾建材では、骨材ヤードに上屋を設け、日光の直射を防いでいます⛱

★減水剤、AE減水剤および流動化剤はJIS A 6204に適合する
遅延形のものを用いることを標準とする。また、高性能AE減水剤は、
JIS A 6204に適合するものを用いることを標準とする
標準示方書【施工編】では、
「減水剤あるいはAE減水剤を使用する場合、標準形に代えて
遅延形のものを使用することを標準とする」と定められています。
当社では、AE減水剤を標準形から遅延形に切り替えることで
夏期におけるコンクリート打設に対応しています😀
★コンクリートの運搬は、コンクリートの温度上昇および
乾燥が少なくなるような装置、方法によらなければならない
暑中コンクリートでは、運搬時のコンクリートの温度上昇および
乾燥が通常に比べて大きくなるため、そうした影響が少なくなるような装置、
方法を用いるとともに、コンクリートをなるべく早く輸送して打ち込むのが
よいとされています。
JIS A 5308「レディ―ミクストコンクリート」では、
生産者が練混ぜを開始してから
運搬車が荷下ろし地点に到着するまでの時間を、
1.5時間以内とすると規定しています。
しかし、暑中コンクリートの場合には、
打込み終了までの時間が1.5時間以内であることを原則としています。
このため、暑中コンクリートとなることが想定される場合には、
使用する工場、運搬経路、運搬時間を検討し、工場との協議により
運搬時間をなるべく短くできるように対策を講じる必要があります。
現在、松尾建材では配送エリアを制限し、生コンの品質を落とすことなく
お客様の施工時間をしっかり確保できるよう努めております!

また、ミキサー車のドラムには遮熱塗料による塗装を施しており、
待機中には適宜ドラムへの散水を行うなどの工夫を行っております😀
2022年07月02日暑中コンクリート|土木工事編①
7月~9月は、両工場において
夏期配合に切り替えて出荷しています!⛱
気温上昇は、コンクリートの性能・施工性に多大な影響を与えるとされ、
土木・建築それぞれに標準仕様(示方)書にその対策について
標準が定められています。
今回から数回にかけて、暑中コンクリートの製造・施工の標準についての解説と
当社での取り組みについてご紹介いたします😃
まずは、土木学会が定める
「2017年制定 コンクリート標準示方書【施工編】」を解説していきます。

★日平均気温が25℃を超える時期に施工することが想定される場合には、暑中コンクリートとしての施工を行うことを標準とする
一般に、「暑中コンクリート=夏に打設するコンクリート」ではありますが、その逆は必ずとも真ではありません。
「日平均気温が25℃を超える時期=夏」と仮定して、昨年の気象庁のデータを参照すると
北海道の夏は7月中旬から8月初旬の3週間ほどと短く、反対に、沖縄の夏は5月初旬から10月中旬までの約5か月と長いです。
そのため、全国的に「〇日から〇日までが暑中コンクリート期間」と定めることは困難です。
しかし、コンクリートの打込み時における気温が30℃を超えると、
スランプ等、コンクリートの諸性状の変化が顕著になると言われています。
日平均気温が25℃を超える時期に施工する場合には、一般に暑中コンクリートとしての施工計画を立て、施工を行うことが
望ましいとされ、十分に時間的余裕をもって実施するのがよいと定められています。
ここ数年、温暖化のためか猛暑が続いており、日平均気温の上がり始める時期も前倒しになってきている印象があります。
弊社でもお客様からもご要望があり、現在、適用期間の見直しを検討しております。
★暑中コンクリートの施工にあたっては、高温によるコンクリートの品質の低下がないように、
材料、配合、練混ぜ、運搬、打込み、および養生等について、適切な処置をとらなければならない
気温が高いと、それに伴ってコンクリートの温度も高くなります🥵
コンクリート温度が高くなると、運搬中のスランプの低下、連行空気量の減少、
コールドジョイントの発生、表面の水分の急激な蒸発によるひび割れの発生、
温度ひび割れの発生等の危険性が増します😨
このため、打込み時および打込み直後において、できるだけコンクリートの
温度が低くなるように、材料の取扱い、配合、練混ぜ、運搬、打込みおよび
養生等について特別の配慮が必要であるとされています。
材料の取扱いから運搬までの温度上昇対策として、
松尾建材が取り組んでいることについては、次回でご紹介します!
また、気温が高い施工環境下では、
通常よりも作業効率が低下しやすいことや作業員の方が熱中症になりやすいことなどにも十分配慮し、
施工計画を立てて適切に管理することが望ましいとされています🤔